ファミリーキャンプに出かけるとき、「これも要るかも」「あれも使うかも」と荷物がどんどん増えてしまう…そんな経験、ありませんか?
ところが実際には、「持ってきたけど一度も使わなかった」「むしろ邪魔だった」というアイテムもたくさんあるんです。
この記事では、初心者がやりがちな持ちすぎミスから、ベテランキャンパーが教える「持っていかなくていいもの」まで、ファミリーキャンプの荷物をスッキリさせるためのヒントをたっぷりご紹介!
次のキャンプをもっと快適に、もっと楽しくするために、ぜひチェックしておきたい情報が満載です!
家族キャンプで“実は使わなかった”アイテムとは?
クーラーボックスが2個はいらなかった理由
キャンプに行くとき、「食材をたくさん持って行こう!」という気持ちから、ついクーラーボックスを2個用意してしまう家庭も多いです。ですが、実際に使ってみると「1つで十分だった…」というケースが非常に多いのです。特に春や秋など、そこまで気温が高くない季節では、クーラーボックスの保冷力も長持ちするため、1つで食材や飲み物をまかなえます。
さらに、クーラーボックスは意外と場所をとるうえに、重量もあるため移動や設置が大変。車の積載スペースも圧迫します。その結果、ほかの必要な道具を入れにくくなってしまうことも。また、キャンプ場によっては売店が充実していたり、近くにコンビニやスーパーがある場合もあります。そういった場所なら、現地調達が可能なため、わざわざ大量に食材を持ち込む必要もないのです。
家族全員で「何をどれくらい食べるか?」を事前に話し合い、1個のクーラーボックスに収まる範囲で持っていくと、無駄がなくなり快適なキャンプができます。
大型テーブルは荷物になるだけ?
アウトドア用の大きなテーブルは、みんなで食事をしたり、道具を広げたりするのに便利そうに思えますが、実は「大きすぎて邪魔だった」という声が多いアイテムです。特に家族4人程度のキャンプであれば、中型サイズのテーブルで十分なことが多く、しかも大型タイプは重たく、持ち運びも大変です。
さらに設置スペースも必要になるため、テントの近くに設置できないこともあり、結局あまり使わなかった…というパターンもよくあります。また、焚き火台や調理スペースなど、他のアイテムと場所の取り合いになるケースも多いです。
最近では「コンパクトに折りたためて軽量なテーブル」が主流になってきており、テーブルを複数に分けて使うスタイルの方が便利なことも。大は小を兼ねる…と思いがちですが、キャンプでは逆に不便になることもあるので注意しましょう。
調味料の持ちすぎ問題
キャンプでの食事は特別感があって楽しいですが、張り切りすぎて「家のキッチンか!?」と思うほど調味料を持ってきてしまう人もいます。醤油、塩、コショウ、味噌、焼き肉のたれ、オリーブオイル、スパイス類…など、ありとあらゆる調味料をバッグに詰め込むのはNGです。
なぜなら、実際には2~3種類の調味料しか使わないことがほとんど。また、ガラス瓶など重くて割れやすい容器も多く、持ち運びには不向きです。キャンプ飯はシンプルな味付けが一番おいしく感じられるもの。自然の中で食べるだけで美味しさが倍増するので、複雑な味付けは必要ないことが多いです。
おすすめは、小分けタイプの調味料を持って行くこと。100円ショップでも売っている詰め替え容器に入れれば、量も調整できて無駄がありません。持ちすぎた調味料はそのまま残って、帰ってからの片づけが面倒になることも。シンプルで厳選したラインナップにしましょう。
着替えが多すぎた失敗談
小さなお子さんがいるファミリーキャンプでは、「万が一のために…」と着替えを多めに持っていくのはよくあることです。しかし、1泊2日のキャンプであれば、そこまでたくさんの服は必要ありません。天気が安定していれば、1セットの着替えで十分なことも。
特に肌着やTシャツ、ズボンを何枚も用意して、結局半分以上着なかったという話はよくあります。洋服はかさばるうえ、キャンプ場では思ったより汚れません。少しの汚れは気にしない、という気持ちの余裕も大切です。
おすすめは、予備の着替えを圧縮袋に入れてコンパクトにする方法。さらに「水遊びをする予定がある」「雨が降る可能性がある」など、天候やアクティビティに合わせて調整しましょう。使わない服を山ほど持って行って後悔するよりも、少ない服で快適に過ごす方がずっとスマートです。
キャンプ用ランタン、そんなに要る?
「暗くなると危ないから」と、キャンプ用ランタンを何個も用意していませんか? 確かに、暗いキャンプ場での灯りは重要ですが、実際にはメインランタン1つとサブ用に小型のLEDライトがあれば十分なケースが多いです。
特に最近のLEDランタンは高性能で、1台でかなり広い範囲を照らしてくれます。また、ヘッドライトやハンディライトも便利なので、人数分の大きなランタンは不要です。それどころか、あちこちにランタンを置くと、逆に明るすぎて虫が集まってくるというデメリットも。
過剰にランタンを持って行くと、収納にも困りますし、電池の管理も面倒になります。使う場所をしっかり決めて、必要最小限に抑えるのが快適なキャンプのコツです。
初心者がついやりがちな「荷物の持ちすぎ」ミス
「とりあえず持っていこう」が失敗の元
キャンプ初心者にありがちなのが、「もしかしたら使うかも」「念のため」と考えて、とにかくいろんなものを持っていくことです。でもその結果、車は荷物でパンパン、現地での設営にも時間がかかり、撤収時もグッタリしてしまう…というのはよくある話です。
特にファミリーキャンプでは、子どもやパパママの荷物が個別に増えていく傾向があります。「子どもが飽きたら困るから」と大量のおもちゃ、「寒かったら…」と大量のブランケット、「何かあったら…」と工具類やガジェット…。気づけば一泊二日とは思えない量の荷物に。
しかし実際には、キャンプの道具はシンプルにまとめるのが一番快適です。必要最低限のアイテムだけを厳選し、足りなければ次回に追加するくらいの感覚がベスト。チェックリストを作って、あらかじめ「絶対に使うもの」だけを入れていくスタイルがおすすめです。
特に初めてのキャンプは、試しに少ない荷物で挑戦してみると、「何が本当に必要か」が体感できます。「とりあえず」ではなく、「これが必要」という理由を持って持ち物を選ぶことが、失敗しないキャンプの第一歩です。
子どものおもちゃは本当に必要?
ファミリーキャンプで悩ましいのが、子どものおもちゃ問題。普段から使っているお気に入りのおもちゃを持っていきたがる子も多く、親としても「退屈したら可哀そうだし…」とつい多めに持って行ってしまいがちです。
しかし自然の中には、子どもにとって夢中になれる“遊び”がたくさんあります。川遊び、虫取り、石拾い、落ち葉を使ったアート…市販のおもちゃがなくても、キャンプ場にはワクワクの宝庫が広がっているのです。結果として「持ってきたけど全然遊ばなかった」という声も多く聞きます。
もちろん、移動中の退屈しのぎや、雨天時の室内遊びとして、小さめの絵本やカードゲームなど1〜2個持っていくのは◎。でもそれ以上は不要です。逆にあまりに多く持っていくと、片づけや管理が大変になり、親の負担も増えてしまいます。
おすすめは「自然の中で遊ぶ」という前提でスケジュールを組み、おもちゃは“保険”程度にすること。キャンプならではの体験を大事にして、子どもの創造力を引き出す遊び方にシフトしていきましょう。
安眠グッズの罠
「寝袋だけじゃ心配だから」と、キャンプ用マットに加えて枕、毛布、クッション、ブランケット…と、寝具系アイテムをどっさり持っていく人が多いですが、実はこれが大きな荷物の原因になりやすい落とし穴です。
確かに快眠は大切ですが、アウトドアの寝具はコンパクト&多用途が基本。特にブランケットや毛布はかさばるうえに重く、天候によっては使わないことも。枕も、タオルを丸めれば代用可能ですし、寝袋によってはフード部分が枕代わりになるタイプもあります。
また、寝具を持ちすぎるとテント内のスペースも狭くなり、家族で寝るには圧迫感が出てしまいます。ファミリーキャンプの場合は「床冷え対策」と「コンパクト性」を両立させたマットを用意し、プラス1枚のブランケットくらいで十分です。
コンパクトなエアーマットやウレタンマットなど、軽量で収納性に優れたアイテムを選ぶことで、荷物がぐっと減ります。「持っていないと不安」よりも、「使わなかったら損」にならないよう、事前に必要性をチェックしましょう。
電気系ガジェットは厳選しよう
スマートフォン、ポータブル電源、モバイルバッテリー、LEDライト、Bluetoothスピーカー、タブレット、ドローン…。現代のキャンプでは電気系のガジェットを多く持ち込む人が増えていますが、これは荷物が増える大きな原因です。
とくにポータブル電源などは重たく、バッテリー容量も事前に計算しておかないと「全然使わなかった」こともあります。Bluetoothスピーカーも、自然の静けさを楽しむキャンプには必ずしも必要ではなく、周囲の迷惑になる場合も。
ガジェット類は「本当に使うか?」をよく見極めることが大切です。キャンプでは電波が弱いこともあるため、タブレットで動画を見る計画が崩れることもあります。また、電源を確保するために延長コードや変換アダプターなどを追加していくと、どんどん荷物が増えていきます。
おすすめは、スマホと小型のモバイルバッテリーだけに絞ること。必要な情報は事前にオフラインで保存しておくと安心です。自然の中では、デジタル機器から少し離れて、家族との会話や体験に集中する時間を大切にしましょう。
大量の調理器具、全部使ってる?
「本格的なキャンプ飯に挑戦したい!」という思いから、フライパンに鍋、ダッチオーブン、焼き網、トング、スパチュラ、お玉、包丁…と、調理器具をどっさり持っていく人がいます。でも、実際には「全部使う時間がなかった」という声も多いです。
キャンプは料理に時間をかけすぎると、設営・片付け・遊びなどとのバランスが崩れてしまいます。とくにファミリーキャンプでは、子どもの相手をしながらの調理になるので、調理道具をあれこれ使い分ける余裕がありません。
おすすめは、「ワンプレートで済むメニュー」や「焼くだけ・煮るだけ」で作れるメニューを選び、使う調理器具を最小限に絞ること。フライパン1つでも十分に美味しい料理ができますし、調理後の洗い物も減らせます。
また、シェラカップやメスティンなど、多機能に使えるアイテムを選ぶことで、荷物を減らせます。たくさんの道具を持って行って後悔するより、少ない道具で工夫して料理するほうが、達成感も大きいですよ。
ベテランキャンパーに聞いた「持って行かないものリスト」
実際に置いていったものTOP5
ベテランキャンパーほど、「これは要らなかったな」という経験を積み重ねて、荷物をどんどんシンプルにしています。そんな経験者たちが実際に「もう持って行かない」と判断したものを5つ紹介します。
- 電気式の調理家電
ホットプレートや炊飯器などは便利そうに思えますが、キャンプ場では電源の確保が難しいことも多く、結局使えなかったという声が多数。また、重たくてかさばるので、アウトドア向きではありません。 - ファンシーなテーブルクロスや装飾品
インスタ映えを狙って持っていきたくなる装飾グッズ。しかし、風で飛ばされたり、食事の邪魔になったりすることも多く、「見栄え重視より実用性」との声が多く聞かれます。 - 大量の予備バッテリー・電池
備えあれば…とは言いますが、使う予定のない電池やバッテリーを何種類も持っていくのは非効率。自分の道具に必要なサイズと個数を確認し、最小限に絞るのがベストです。 - 予備のテントやタープ
「急に雨が降ったら」「日よけが足りなかったら」と2張り目を用意する人もいますが、設営と撤収の手間を考えると使わない場合は大きな負担。天気予報や場所に合わせて判断しましょう。 - 普段使わないアウトドア専用グッズ
例えば特殊な調味料ボトルや専用グローブなど、キャンプ用として売られていても、日常で使っていないものは使い方に迷いがち。代用品があれば持ち込まないというのが経験者の知恵です。
こうした「実は必要なかったもの」を知ることで、初めてのキャンプでも荷物を減らして快適に過ごせます。
利便性よりコンパクトさを重視する理由
キャンプでは「便利なもの」よりも「コンパクトで軽いもの」が重宝されます。理由はとてもシンプルで、荷物が多すぎるとキャンプそのものが疲れるイベントになってしまうからです。
例えば、折りたたみ式の大きなイスや広々した調理台は確かに快適ですが、持ち運びと収納を考えるとかなりのスペースを取ります。その分、移動や設営・撤収が大変になり、「使わないけど片付けは必要」という状況にもなりかねません。
一方、軽量で多機能なアイテムは、1つで何役もこなせるうえ、荷物もコンパクトにまとまります。たとえば「チェア+収納+サイドテーブル」になるスツールや、メスティンのように「炊飯+炒め物+お皿」が1つで完結する調理器具などがその代表例です。
また、子連れファミリーでは、大人がどれだけ効率的に動けるかが重要。荷物が少ないほど、設営中に子どもの相手をする余裕もでき、安全面でも目が届きやすくなります。
「便利そうだから」ではなく、「使う頻度が高くて軽いものか?」という視点で選ぶことが、ベテランたちの共通した考え方です。
「代用できるもの」を見極めるコツ
キャンプの持ち物を減らすためには、「専用品をそろえる」よりも、「代用できるものがないか?」という発想が重要です。これはベテランキャンパーたちが長年の経験で身につけた知恵でもあります。
例えば、まな板。キャンプ用の折りたたみまな板も便利ですが、実はタッパーのフタでも代用可能。包丁もアウトドア専用のものをわざわざ買わなくても、家にあるペティナイフで十分なことが多いです。
また、食器類も、紙皿や使い捨て容器ではなく、シェラカップで“調理・食事・カップ”を兼ねることで荷物を減らせます。ブランケットやタオルも、イスのクッション代わりや日よけなど、複数の用途で使えるものを選ぶと便利です。
この「一石二鳥」「一つで三役」がアウトドアではとても大切。持ち物に多機能性があると、それだけで荷物は半分近くに減らせます。初めてのキャンプでは、道具の紹介よりも「代用できるかどうか」を意識してみましょう。
必要最低限のアイテムリストとは?
「これは絶対に持っていくべき!」という最低限のアイテムリストを知っておくと、初心者でも安心して荷物を厳選できます。以下が、ベテランキャンパーが口を揃えて勧める最低限アイテムです。
| カテゴリ | アイテム例 |
|---|---|
| 寝具 | 寝袋、マット(断熱性あり) |
| 調理 | シングルバーナー、メスティン or フライパン、カトラリー |
| 照明 | LEDランタン、ヘッドライト |
| 衛生 | ウェットティッシュ、ゴミ袋、歯ブラシセット |
| 緊急用 | 救急セット、虫除けスプレー、常備薬 |
これに加えて、天候や場所によって調整するのが基本です。たくさん道具があっても、使いこなせなければ意味がありません。まずはこのリストを基に、必要なものだけを持ち込み、回数を重ねるごとに自分なりの“厳選アイテム”を増やしていくと良いでしょう。
不要な荷物が減るとキャンプがもっと楽しい!
キャンプを楽しむうえで、実は「不要な荷物を減らすこと」が快適さを大きく左右します。なぜなら、荷物が少なければ設営も撤収も短時間で済み、その分、自然の中でのんびりする時間が増えるからです。
たとえば、片づけが早く終われば、朝ゆっくりコーヒーを飲む時間ができたり、帰りの道中に温泉に立ち寄る余裕も生まれます。荷物が多いとどうしても「準備と片づけに追われるキャンプ」になり、楽しさより疲れが残る結果になりがちです。
また、家族全員で荷物の分担もしやすくなり、子どもも「お手伝い」がしやすくなります。荷物が多いと大人にしかできない作業が増えてしまいますが、少ない荷物なら子どもも率先して手伝える機会が増え、家族での一体感も高まります。
キャンプは「非日常」を楽しむ時間。荷物を減らして、その分、心の余裕と時間のゆとりを増やす。これが、ベテランキャンパーが実感する“本当に楽しいキャンプ”のコツなのです。
「あれば便利」は本当に必要?判断基準を徹底解説
使用頻度の低いものはNG
キャンプの持ち物を選ぶときに、「あれば便利かも」と思って詰め込んだ道具の多くが、実は一度も使われずに終わることがあります。ベテランキャンパーがよく言うのは、「1泊2日のキャンプで1回も使わないものは、そもそも必要ない可能性が高い」ということです。
たとえば、特殊な調理器具や複数のナイフ類、計量スプーン、パスタ鍋など…。家庭では便利でも、キャンプ場では使い勝手が悪く、かえって手間になることがあります。また、収納場所を圧迫し、他の重要な道具の出し入れが面倒になることも。
使用頻度の低いものを持ち込むと、準備・設営・撤収のどこかで「やっぱり邪魔だった」と感じるケースが非常に多いです。そこでおすすめなのは、事前に「これは何に使う?」「使う頻度は?」と自問自答するチェック方式。1泊の中で3回以上使う可能性があるかを判断の基準にしてみましょう。
「あると便利」と「なくても困らない」は全く違うもの。キャンプでは「なくても平気だった」を積み重ねて、どんどん持ち物を精査していくスタイルがベストです。
道具が増えるほど手間も増える
キャンプでは、「道具が増える=便利になる」と考えがちですが、実際には道具が多いほど準備・設営・撤収にかかる手間が増えてしまいます。特に子連れのファミリーキャンプでは、大人がすべての段取りをしなければならないケースも多く、その分、体力も時間も消耗してしまいます。
例えば、調理器具をたくさん持っていった場合、それぞれの収納ケースや洗い物、火の管理なども必要になります。照明を多く用意すれば、設置場所や電池の管理も増えます。こうした「管理の手間」が重なると、せっかくの自然の中でのんびりする時間がどんどん削られていきます。
また、道具が多いと紛失や忘れ物のリスクも高まります。「どこにしまったっけ?」「あれ、電池入れてたっけ?」と探し物に時間を取られるのは非常にもったいないですよね。
ベテランキャンパーが目指すのは、“最小限の道具で最大限の快適さ”です。道具を絞ることで、片付けも簡単になり、子どもたちも手伝いやすくなります。結果的に、家族全員がリラックスしてキャンプを楽しめるようになります。
天気や場所に合わせた荷物選び
キャンプに必要な持ち物は、季節や天気、そしてキャンプ場の環境によって大きく変わります。「いつも使うから」といった感覚で荷物を選んでしまうと、必要のないものまで持っていってしまう原因になります。
たとえば、春や秋で涼しい時期なら防寒対策は必要ですが、真夏のキャンプ場では厚手のブランケットや湯たんぽはまず使いません。また、山間部では虫除けスプレーや長袖が必須になりますが、海辺では日焼け止めやサンダルが大事になるなど、環境によって最適な持ち物は異なります。
天気予報をしっかり確認し、「今回は雨の心配がない」「最低気温は何度ぐらいか」など、事前情報をもとに荷物を調整しましょう。雨が降る可能性があるときだけタープやレインウェアを追加するなど、“必要なものだけを持っていく”というスタイルが、荷物をスリムにするコツです。
特にファミリーキャンプでは、子どもの快適さを重視して荷物が増えがちですが、「本当に必要なものは何か?」を天気と場所で見極めていくと、自然と荷物は軽くなります。
持ち物を“シェア”する発想
荷物を減らすうえで有効なのが、「シェアする」という考え方です。これは家族内だけでなく、グループキャンプでも使えるテクニックです。たとえば、ランタンや調理器具、タープなど、大型で1つあれば十分なアイテムは、家族で共用することで荷物をかなり減らすことができます。
小さな子どもがいる家庭では、「子ども用の食器」「タオル」「椅子」なども、すべて人数分そろえなくても回して使えることが多いです。特に一泊程度なら、交代で使うスタイルでもまったく不便に感じません。
また、他の家族とグループでキャンプに行く場合は、「誰が何を持っていくか」を事前に話し合っておくのがポイント。全員がクーラーボックスを持ってきたり、テーブルを持ち寄ったりすると、大量の荷物になってしまいます。シェアすることで、スペースにも余裕が生まれます。
シェアのメリットは、「軽量化」だけでなく、「交流」や「助け合い」が自然と生まれることにもあります。キャンプは家族だけの時間でもあり、人とのつながりを感じられる場でもあります。シェアの考え方で、より豊かなキャンプ体験ができるようになりますよ。
家族で話し合って決める荷物の優先順位
ファミリーキャンプでは、荷物の準備をお父さんやお母さん1人で抱え込まず、家族全員で話し合って「何が必要か?」を決めることがとても大切です。そうすることで、荷物の数も減り、誰が何を使うかが明確になって無駄がなくなります。
例えば、テント内で使う寝具にしても、「子どもは寝袋の方が楽しい」「ママはマットが欲しい」など、それぞれの意見を取り入れることで、本当に必要なものが見えてきます。また、「あれもこれも持っていきたい」という気持ちがあっても、優先順位を決めることで取捨選択がしやすくなります。
子どもにも「自分のリュックには何を入れるか?」を決めさせて、持ちすぎない練習をさせるのも良い経験です。キャンプの荷物準備から参加させることで、責任感や協調性も育ちます。
チェックリストを紙に書いて、家族みんなで“いる・いらない”を話し合うのもおすすめの方法です。家族全員の意見を尊重しながら決めることで、荷物の数が自然と減り、結果的に快適なキャンプになります。
スッキリ荷物で快適キャンプ!いらないものチェックリスト付き
持ち物をリスト化して見える化
キャンプの準備でよくある失敗が、「何を持っていけばいいか分からない」「持ちすぎたor忘れ物をした」です。これを防ぐには、“持ち物リストの見える化”がとても有効です。特にファミリーキャンプでは、人数が多いぶん必要なアイテムも増えるので、リストなしでは管理が難しくなります。
リスト化のメリットは、必要なものを明確にできること。そして、「これは本当に要る?」「代用できる?」といった取捨選択の視点を持てることです。最初はインターネットで公開されているキャンプリストを参考にしてOKですが、何度か経験を重ねるうちに、自分たち家族専用のカスタムリストにしていくのが理想です。
おすすめは、チェックボックス付きのリストを印刷して使うこと。スマホのメモアプリでもいいですが、紙で見える形にすると家族で共有しやすく、子どもも「これ持ったよ!」と楽しみながら準備に参加できます。
荷物を持ちすぎないためには、「持っていく理由」を書くのもおすすめ。たとえば「寝袋(夜冷えるため)」など、理由がなければ持っていかないというルールを決めておくと、自然と荷物は減っていきます。
荷物を減らすメリットとは?
キャンプの荷物を減らすことで得られるメリットは数多くあります。まず一番大きいのは、移動と設営が圧倒的にラクになるということ。特に小さな子どもがいるファミリーにとって、キャンプ当日はバタバタしがちですが、荷物が少ないだけで心にも体にも余裕ができます。
次に、車の積載スペースにゆとりが生まれること。クーラーボックスやテントなど、大型のアイテムはどうしても必要ですが、それ以外を減らせばトランクに詰め込むストレスも軽減。燃費も多少よくなります。
また、片付けの時間が短くなるのも大きな魅力です。撤収時は特に疲れが出てくる時間帯。そんなときに大量の道具をひとつひとつ片づけていると、楽しさより疲れの記憶が残ってしまいます。荷物が少なければ、撤収もスムーズになり、最後まで気持ちよく終われます。
さらに、使う道具に集中できることで、自然と道具への愛着が湧きます。本当に必要なものだけを使って快適に過ごせるようになると、「あれもこれも欲しい」という欲求も落ち着きますよ。
家族ごとのチェック項目例
ファミリーキャンプでは、家族の人数や年齢構成によって必要なものが変わります。そこで「家族ごとのチェック項目例」を知っておくと、自分たちに合った持ち物が選びやすくなります。
例:4人家族(パパ・ママ・小学生・幼児)
| カテゴリ | 持ち物例 | 注意ポイント |
|---|---|---|
| 寝具 | 寝袋×4、マット×4 | 圧縮して持ち運びやすく |
| 食事 | カトラリー×4、鍋、フライパン | ワンプレートで済むメニュー推奨 |
| 洋服 | 着替え各1セット、予備下着 | 雨具は全員分準備 |
| 遊び道具 | 虫取り網、トランプ | 持ちすぎないよう厳選 |
| 衛生用品 | 歯ブラシ、ウェットティッシュ | 子ども用に小さめサイズも用意 |
| 緊急用 | 虫除け、かゆみ止め、絆創膏 | 子ども用薬も忘れずに |
こうした表を家族ごとに作っておくと、荷物が無駄なくそろえられるうえに、準備の抜け漏れも防げます。
リスト化で迷わず準備ができる
リスト化の最大の魅力は、「準備に迷わなくなること」です。キャンプ前日は何かと慌ただしく、「あれも要るかも」「これ持ったっけ?」と気持ちが落ち着かなくなります。そんなとき、チェックリストがあるだけで冷静に準備が進められます。
特に家族全員でリストを共有しておけば、それぞれの担当を決めることができ、「ママは調理系、パパは設営道具、子どもは遊び道具」など分担して準備ができます。すると準備時間も短縮され、出発までのストレスも激減。
リストには、「使用頻度順」や「使用するシーン別」に並べる工夫を加えると、より実用的になります。たとえば、「設営に使う道具→食事→寝具→遊び→緊急用品」という並びにすると、現地でもスムーズに行動できます。
また、使用後の振り返りとして、「実際に使った・使わなかった」をメモしておけば、次回以降の準備に生かせます。こうして“進化するリスト”を持つことで、キャンプの快適さはどんどん向上していきます。
PDFで印刷できる持ち物チェックリスト
実際にキャンプに行くときは、スマホで見るより紙のチェックリストが断然便利です。そこで、印刷して使えるPDF形式のチェックリストを用意しておくのがベストです。以下は、シンプルで実用的な例です。
✅ ファミリーキャンプ持ち物チェックリスト(一部抜粋)
| チェック | カテゴリ | 持ち物 |
|---|---|---|
| ☐ | テント類 | テント本体、ペグ、ハンマー |
| ☐ | 寝具 | 寝袋、マット、枕(または代用品) |
| ☐ | 調理 | バーナー、鍋、カトラリー、食器 |
| ☐ | 照明 | ランタン、ヘッドライト、予備電池 |
| ☐ | 衛生 | 歯ブラシ、ウェットティッシュ、タオル |
| ☐ | 服装 | 着替え、防寒具、雨具 |
| ☐ | 子ども用品 | おむつ、遊び道具、絵本 |
| ☐ | 緊急 | 救急セット、虫除け、常備薬 |
このようなリストを自宅で印刷して、家族でチェックしながら準備することで、「いらないものを持たないキャンプ」が実現します。PDF化して保存しておけば、毎回のキャンプで再利用できてとても便利です。
まとめ:荷物を減らすことで、キャンプはもっと楽しくなる!
ファミリーキャンプでは、ついつい「あれもこれも」と持って行きたくなりますが、実は「持っていかなかった方が快適だった」と感じるものが意外と多いのが現実です。
この記事では、実際に使わなかったアイテムや、初心者がやりがちな失敗例、ベテランキャンパーの声から見えてくる「いらないもの」について具体的に紹介してきました。そして、「あれば便利」な道具が本当に必要かどうかの見極め方や、チェックリストの活用法も解説しました。
荷物を減らすことで、移動も設営も撤収もスムーズになり、家族との時間や自然の中でのんびりした時間がグッと増えます。なにより、準備や片付けのストレスが減ることで、心から「また行きたい!」と思えるキャンプになるのです。
次のキャンプからは、ぜひこの記事を参考に「いらないもの」を見直してみてください。軽やかで快適なファミリーキャンプを、あなたのご家族でも実現できますよ。
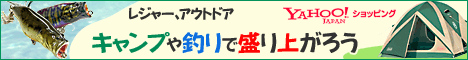




コメント